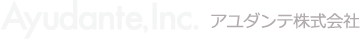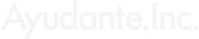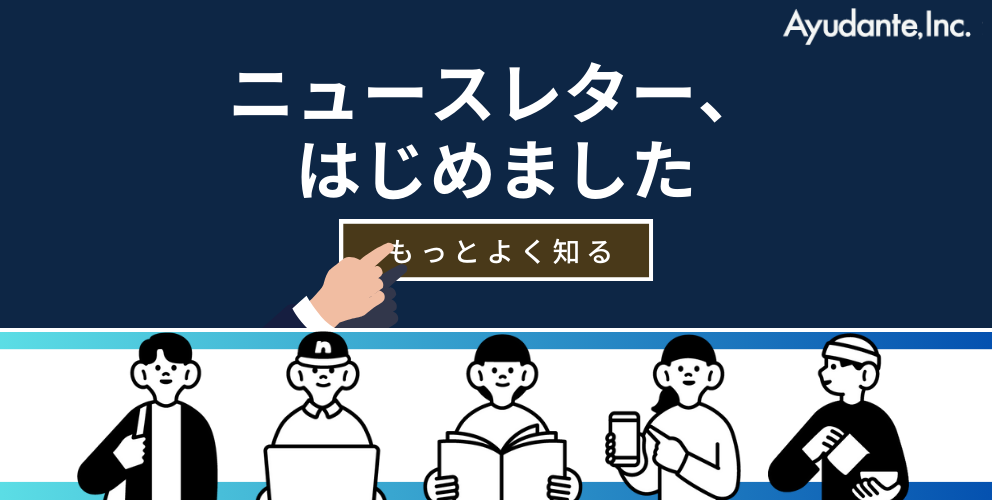本コラムはAYUDANTE NEWS 2025年2月号を全編公開でお送りしております。
ニュースレター公開から半年経過したため全編公開でお送りいたします。
本記事の内容は公開時点での2025年2月26日時点での情報となります。
生成系AI検索が相次いでサービスを開始する中、検索エンジンの未来はどうなるのか。
このテーマについて、株式会社Digital Evangelistの金谷武明氏、弊社社長・安川洋、そしてファシリテーターを務める CSO・大内範行 が徹底討議しました。
生成AI検索とは?
2024年から複数の生成系AIサービスがウェブ検索を導入する動きが活発です。OpenAIがChatGPTに検索機能をリリース、また、Perplexityなども検索サービスを開始しました。これらの生成AI提供企業がリリースした検索サービスを生成AI検索と呼んでいます。
Googleの検索エンジンシェアは生成AIで下がる?
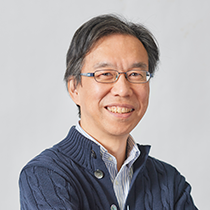
OpenAIはこの20日、利用者が4億人を超えたと発表しました。ChatGPTはじめ生成AI企業は、インターネット検索サービスに参入しています。
この動きを受けて、Google検索エンジンの市場シェアが低下するのではないか? という予測が出はじめています。二人の見方はどうですか?

似た質問を結構されます。
Google検索が20年ぐらい高いシェアを維持している中で、生成AIが検索サービスを始めました。いよいよGoogle検索の王者の座が揺らぐんじゃないかと、そう考えている人もいます。でも実際はどうなるのか、私もいろんな角度から考えています。
生成AI検索の利用は、徐々にですが増えていくと考えています。ただ、一方で GoogleもAI Overviewsなどを取り入れて、UIの変更にも取り組んでいます。
私は短期的には、一部の人たちの利用に留まって、一般の人々にはまだ広がらないと考えています。それほどシェアに劇的な変化は起きないだろうと思います。

AIそのものの活用は今年来年と劇的に増えていくと予想していますが、検索サービスのような汎用的なサービスの利用が増えるかは疑問です。
今の生成AIは、一応なんでも答えてくれますが、無難な答えで正直役に立たない。なんでもできる状態のままでは、一般の人々にはそれほど普及しないでしょう。
モノや特定の目的のサービスに組み込まれるなど、利用シーンが明確にわかるものにならないと、爆発的には伸びないと思います。
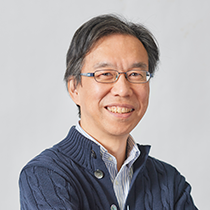
二人とも条件付きですが、逆に何かきっかけがあればシェアが変わる可能性もありますか?

もし、大きな変化が起こるとすれば、それはユーザーの好みで変わるのではなく、社会の大きな変化、あるいは独占禁止法など政府の規制によって変わるのだと考えています。
たとえば、オンライン会議。僕らはずいぶん早くから利用して便利さを実感していましたが、なかなか一般の人は利用しなかった。新型コロナのような社会の変化があって一気に普及しました。
検索の場合は、政府の規制ですね。米国などでは実際にGoogleの分割が議論されています。実際に政府が規制するかはともかく、もしGoogleの分割などがあれば、それがきっかけでシェアが大きく変わる可能性はあるでしょう。
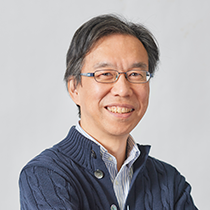
なるほど。昨年、ドイツやフランスなど一部のEUの国でGoogle検索のシェアが低下したというレポート※1がありました。
たとえば、AppleのiPhoneのデフォルト検索が変わったり、デフォルトがなくなって、最初に複数から選ぶようになるだけでシェアの変動はおきますね。
※1:Why Is Google Losing Market Share In The EU? December 3, 2024 Kevin Indig
(Search Engine Journal)

そうした政府の規制には、個人的に賛成できないですね。
EUでブラウザを選ぶUIを見ましたが、多くのブラウザが並んでいて、本当に大丈夫か?と思うブラウザもまじっているような状態です。
面倒だし、品質が悪いサービスやアプリが入り込んだり、誰も幸せになりません。

もし、検索のシェアが変化しても、生成AIがGoogle検索のすべてを置き換えるということはないでしょう。
単純な検索だけが目的じゃないもの。調査した回答がほしいとか、アイディア出しなら、OpenAIのDeepResearchなどにどんどん置き換わっていくでしょう。
もっと単純な検索、ブックマーク代わりの検索とか、ナビゲーショナルクエリなどは、かえって生成AIだと面倒です。
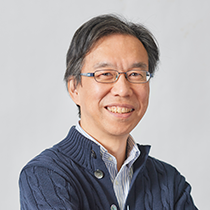
今、もっとも影響を受けているのは、Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイト、米国だとQuoraなどだという調査結果※2も出ています。
※2:The Evolution of Online Search After ChatGPT (Semrush と Statistaによる共同レポート)

検索に限定しなければ、AIの普及は今年来年と劇的に広がっていくと思います。特定の用途なら、LINE並みに浸透するかもしれません。それだけのポテンシャルはあります。
ぱっと思いつくのは、子供たちの利用です。
例えば「この宿題がわからない」と言ったら「教えてあげようか?」とAIと会話が成立します。もしそうなったら、親の私も使うかもしれません。子供がAIぬいぐるみと会話するなんていうことも含めて、子供たちが率先して使い始めるでしょう。
生成系AI検索のビジネスモデルは?
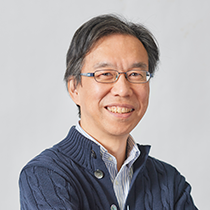
続いて、生成AI検索のビジネスモデルについて、どう見ていますか?
生成AI検索にも広告を導入するというニュースがPerplexlityなどから出ています。

それで大きな収益を上げるのは難しいのではないかと思います。Google検索のようなマネタイズは簡単にはできないでしょう。
Google検索とGoogle広告のビジネスモデルは本当に素晴らしいと思います。最初、Googleが検索をはじめたときはビジネスのことは考えていなくて、みんながハッピーになるような広告を基本としたビジネスモデルは、段階的にできていった。
一方、生成AI検索が投資を回収できるというイメージは持てません。巨大なインフラコストをまかなうためには、OpenAIに対してMicrosoftが資金やインフラを提供したような、パートナーシップ的なものしか思いつきません。
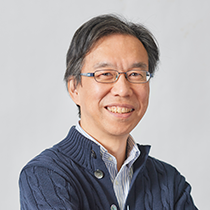
確かに、Google検索は関連がある選択肢を複数出すから、いろんなサイトに飛んでいく。だから広告がはまるという面はあります。Perplexityなんかは検索エンジンじゃなくて、「アンサーエンジン」と言っています。

Google検索はゴールではなくてあくまでもゴールへのヒントを聞きに行ってるので、ヒントとしての広告も関連性が高ければクリックされます。一方で生成AIはそこで答えを得ようと思っているのでその先に何か関連情報があるかも、という広告を出してもなかなかクリックはされないでしょう。少なくとも今の検索連動型広告を置き換えるようなものには現状ならないと考えています。
代わりのビジネスモデルが見つけられるかどうかが、今後の生成AI検索の行方を占うカギですね。

航空券をAIで予約するとき、オトクなキャンペーンを紹介するとか、実際にエージェントが予約までするとか、エージェントを介したトランザクションをビジネスにすることはできるでしょう。
でも、それでコストが賄えるとはとても思えません。一番の問題は電気代。
生成AI検索でトランザクションが完了しても、広告や手数料収益より電気代の方がはるかに高いという状態がしばらく続くでしょうから、電力コストの低減も重要になります。自社発電所を持って、電力コストを抑えないといけません。いかに安く電気を確保するかがカギになってきます。
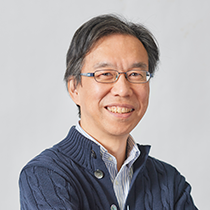
生成AIのChatGPTが1回質問に答えると、Google検索の電力量の約10倍消費するというレポート※3が出ていました。検索でコストをカバーする収益を得るのは相当難しそうです。
※3:Powering Intelligence: Analyzing Artificial Intelligence and Data Center Energy Consumption
(ERPI) 2024年5月28日
Googleの検索エンジンシェアは生成AIで下がる?
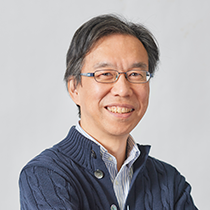
金谷さんは「SIIJ 持続可能なインターネットエコシステムを目指す会」を設立して、持続可能なネット社会の実現を支援する活動にも取り組んでますね。生成AI検索の倫理面の課題はありますか?

SIIJでも集中的に取り上げていますが、やはり現在の検索やSNSは、詐欺広告や低品質コンテンツがもっとも大きな問題のひとつです。
生成AI検索でも同様の問題は出てくると思いますが、今のところはうまく制御できていて、問題はそれほど見えてこない。コンテンツの質の調整は、機能している印象です。

私が日々生成AIを使う中では、正しくない答えも多い。まだまだ本格的な仕事には使えないと感じています。
低品質コンテンツや詐欺を生成AIに提供しても、それほどメリットはない気がします。
それよりも、今後問題になるのは、言論統制ではないでしょうか。中国初のDeepSeekではすでにこうした問題が指摘されています。
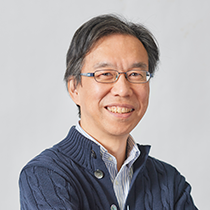
金谷さんが、Googleで検索エンジンのエバンジェリストだったころ、医療系の低品質コンテンツが問題になっていました。生成AI検索でも似た問題は起こりうるのではないでしょうか?

医療系の質問、ダイエットや体調について相談したり、生成AI検索がパーソナルアシスタントとして、人生の大事な相談相手になるのは十分ありえます。今後、問題になる可能性はあると思います。
社会的な問題にしても、人は信じたいものを信じる傾向が強い。偏った生成AIに依存してしまう懸念はあります。

イーロン・マスクも早い段階で、AIのリスクについて、とても危険だと警鐘を鳴らしていました。※4
AIが進化して広がれば、思想や政治、社会への影響は大きくなっていきます。ヒューマノイドロボットが、アドバイザーになれば影響は大きいでしょうね。
※4:イーロン・マスク「AIは死なずに、永遠に生き続ける。そして、私たちが決して逃れることのできない不滅の独裁者が誕生することになる」と2020年に警告
エコシステム
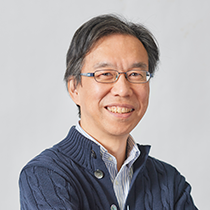
生成AI検索への懸念はエコシステムにもあります。金谷さんが挙げたように、Google検索の広告を中心としたビジネスは、案外幸福なシステムになっていて、コンテンツをネットに出す人たちとのエコシステムもできています。

Googleビジネスのエコシステムがなくなってしまうとしたら大きな問題です。
Google検索からの訪問で、視聴率があるからコンテンツを見てもらえる。
生成AI検索の中で答えが完了してしまうと、コンテンツを作る人の意欲が育ちません。コンテンツづくりへの意欲が薄れれば、ネットのコンテンツの総量や多様な意見が減少してしまいます。
生成AI検索は、レベニューシェアの仕組みを考える使命があります。

Googleがnoteと資本業務提携したのには正直驚きました。特定のコンテンツ提供者に対して不公平という意見もあるのでしょうが、「AIを使って良いコンテンツを作ろう」という流れを推進する狙いもあると思います。今後、どう進んでいくのか注意してみていきたいです。
Googleも、AIで検索や質問に答える方向がどんどん進むので、広告以外の収益化にも何か手を打ってくるかもしれません。
エコシステムが成立せず、例えば個人コンテンツがなくなったら、インターネットは何だったのか、という話になってしまう。
Googleには、ぜひインターネットのエコシステムを守る存在であってほしい。
アユダンテは金谷氏がアドバイザー。
SEOチームは日々、SEOや検索エンジンの議論を金谷氏としています。金谷氏にはコラムも執筆していただき、弊社のお客様向けにお送りしています。一方、弊社代表の安川は子どものころからプログラムを書いていて、テクノロジをアユダンテの根幹に位置づけています。アユダンテは多国籍の技術集団でもあり、プログラマや技術者とも交流ができる環境です。
編集後記
第2回となる Ayudante News をお届けしましたが、皆さまお楽しみいただけましたでしょうか?今回は金谷氏と弊社安川・大内の討議形式でお届けいたしました。
ぜひ皆さまの感想を、ハッシュタグ #アユダンテニュース をつけてX(Twitter)でつぶやいていただけると嬉しいです。ご意見やご感想、お待ちしております!
以下はニュースレター編集部の後記です。小林・大内が交互にお送りいたします。
最近、国立国会図書館のデジタル化が凄いと話題ですね。歴史好きで長く通ってますが、最近はほぼ自宅から使えてしまっています。ホント凄いです。
私の予想では、まもなくサム・アルトマンやイーロン・マスクが目をつけて、国立国会図書館と提携しようと言い出すと思ってます。ぜひ長い歴史を維持する国家として、ちゃんと考えて対応してほしいと思いますです。 /大内
過去のバックナンバー
【AYUDANTE NEWS 2025年1月号】アユダンテSEOチームが重視する2025年のSEO
【AYUDANTE NEWS 2025年2月号】何度目かのGoogle検索エンジン死亡予測、今回は本物か?
【AYUDANTE NEWS 2025年3月号】教えて春山さん!サーバーサイドGTMって何?
【AYUDANTE NEWS 2025年4月号】教えて畑岡さん!GTMのページビューとクリック計測のトリガーの使い分けってどう考えるの?
【AYUDANTE NEWS 2025年5月号】AI時代のGoogle検索にどう対応する?
【AYUDANTE NEWS 2025年6月号】生成AIの広告への活用-7つの役割と活用ノウハウ-
【AYUDANTE NEWS 2025年7月号 抜粋】ヒートマップ初心者の疑問に答える! SEO×広告対談で分かる実践ノウハウ
【AYUDANTE NEWS 2025年8月号 抜粋】SMX Advanced 2025(ボストン)に参加した現地レポート
【AYUDANTE NEWS 2025年9月号 抜粋】AIで進化するGA4 期待される2つの機能
【AYUDANTE NEWS 2025年10月号 抜粋】15年の実践で築いた、広告チームが大切にする3つの価値観
【AYUDANTE NEWS 2025年11月号 抜粋】アユダンテ社内勉強会のテーマはどうやって選んでいるの?
【AYUDANTE NEWS 2025年12月号 抜粋】SEO・広告・/GMP 各チームが“今年おすすめしたい”コラム6選